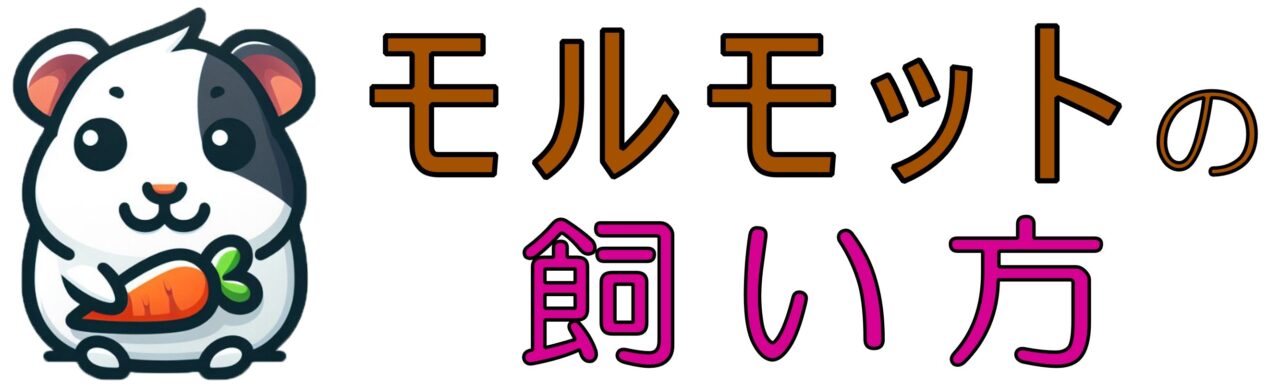現在ではペットとして多くの人に癒やしを与えているモルモットですが、その歴史は長く、人間との関わり方も時代によって大きく異なりました。ここでは、南米での家畜化から世界へ広まるまでの、モルモットと人の歴史を紐解いていきます。
南米での家畜化と食文化
モルモットと人間の歴史は古代インディオが野生のテンジクネズミを家畜化したことから始まります。当時の野生種は、体が小さく頭が大きめで、鼻がとがっており目や耳も大きいなど現在の愛らしい姿とは少し異なる「可愛いとは言い難い」容姿だったと言われています。
当時、南米のアンデス地方では「クイ」と呼ばれ、祝祭時の貴重な食肉用、または愛玩用として飼育されていました。性格がおとなしく、飼育が容易で繁殖力が強かったため家畜として非常に適していたのです。1530年代にスペイン人が南米に到達した際には、インカ帝国ですでに食肉用として広く飼われていたと記録されています。この食文化は現在でもペルーなどで続いています。
ヨーロッパを経由し世界でのペット化の流れ
1500年代~1600年代にかけて、オランダ人やスペイン人、あるいはドイツ兵によってヨーロッパへ持ち込まれたとされています(諸説あり)。ヨーロッパに渡ったモルモットは、その愛らしい姿から次第に愛玩動物として人気を博し、1770年代にはアメリカをはじめ世界中へペットとして広まっていきました。
日本への渡来と普及
日本には1843年(天保14年)、江戸時代にオランダ人によって長崎へもたらされたのが最初とされています。明治、大正時代には愛玩用として普及し、昭和初期には品種も増え、ペットとしての地位を確立していきました。
実験動物としての利用
一方で、日本では愛玩用だけでなく、実験動物としても広く利用される歴史がありました。特に、体内でビタミンCを生成できないという人間と共通の特性を持つことから、結核の研究などに重宝されました。この歴史的背景から、日本では「モルモット=実験動物」というイメージが強く残り、現在でも比喩表現として使われることがあります。
現代におけるモルモット
日本ではウサギやハムスターに比べるとまだ飼育頭数は少ないですが、その穏やかな性格や感情表現の豊かさから、近年ペットとしての人気が再燃しています。海外では非常にポピュラーなペットであり、多くの国で愛されています。食料から実験動物、そして愛玩動物へと、モルモットと人間の関係は時代と共に変化し続けてきたのです。