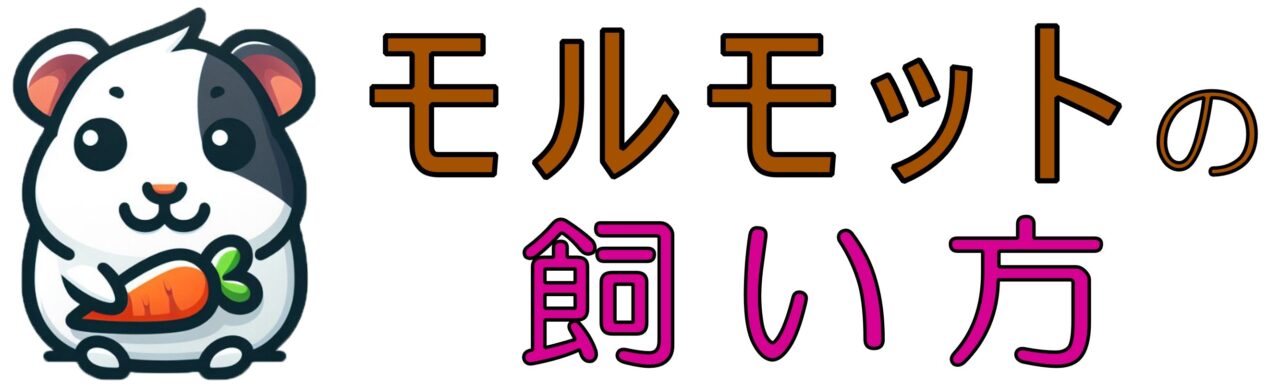「モルモット」というお馴染みの名前。しかし、なぜそう呼ばれるようになったのでしょうか?海外では「ギニーピッグ」というユニークな名前でも知られています。この記事では、モルモットの名前の由来と、世界各地での様々な呼び名についてご紹介します。
目次
日本での呼び名:「モルモット」と「テンジクネズミ」
日本では一般的に「モルモット」と呼ばれています。これは、江戸時代にオランダから持ち込まれた際、オランダ語でアルプス山脈に住む「マーモット」と誤って伝えられ、それが訛って定着したという説が有力です。
また、学会などでは和名である「テンジクネズミ(天竺鼠)」が使われます。これは、遠い異国(天竺)から来たネズミ、という意味合いで名付けられたとされています。
海外での呼び名:「ギニーピッグ」
英語圏では「Guinea Pig(ギニーピッグ)」という名前が一般的です。「ギニアの豚」という意味ですが、これにはいくつかの説があります。
- イギリスに持ち込まれる際に西アフリカのギニアを経由したという説。
- 南米のギアナ(Guiana)が訛ったという説。
「ピッグ」については、ずんぐりした体つきが豚に似ている、鳴き声が豚に似ている、といった説があります。
その他の呼び名
- Cavy(ケイビー): 海外の愛好家の間でよく使われる愛称です。学名「Cavia porcellus」や、アンデス地方での呼び名「Cuy(クイ)」に由来すると言われています。この「クイ」という呼び名は、彼らの「クイクイ」と聞こえる鳴き声がそのまま名前になったという説もあります。
- Meerschweinchen(メールシュヴァインヒェン): ドイツ語で「海を越えてきた小さな豚」という意味です。大航海時代、船上での新鮮な食料としてモルモットが連れてこられた歴史を物語っています。