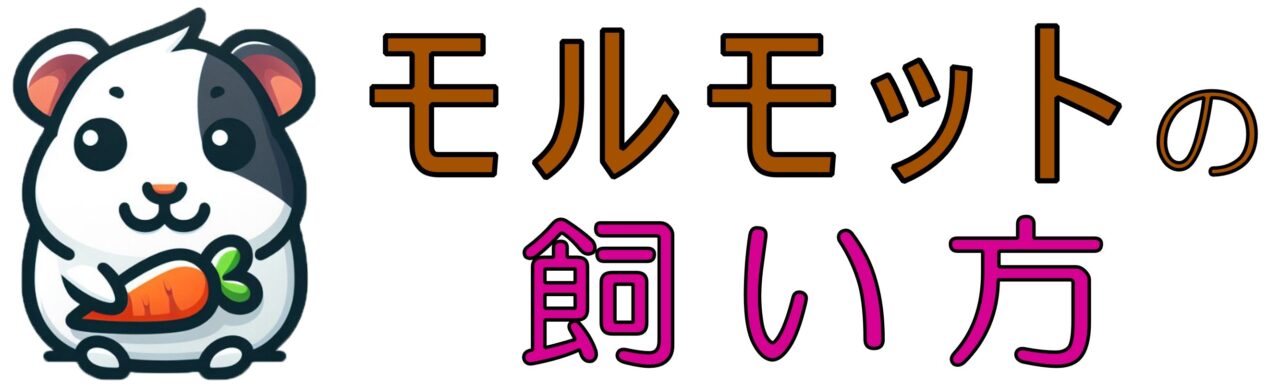モルモットを家族に迎えることが決まったら、次はお部屋の準備です。モルモットが快適で安全に暮らすためには、いくつか専用のグッズを揃える必要があります。この記事では、お迎え初日から必要になる基本的な飼育グッズと、それぞれの選び方のポイントを詳しく解説します。
- お迎え初日から必要になる、全ての飼育グッズの具体的なリストが手に入る
- ケージの最適な広さや床材の選び方など、モルモットの健康と安全を守るための最重要ポイントがわかる
- 「金網の床」や「ペットシーツ」など、見過ごしがちな危険なグッズ選びのポイントを理解し、安全な選択ができる
- 災害時や通院に備えるキャリーや防災グッズ、日々の健康管理に必須の体重計の選び方まで網羅できる
- グッズ選びを通して、モルモットが本当に快適に暮らせる環境を根本から理解できる
ケージ(サイズ・高さ・素材・施錠)
ここでは「住まい選び」の基本をまとめます。モルモットは走って、食べて、隠れて…と、暮らしのほとんどをこの空間で過ごすため、ケージの広さと安全性が、その子の心と体の健康にまっすぐつながります。まずは必要な面積と高さ、素材の向き不向き、施錠のコツを押さえておきましょう。あとから買い替えるより、最初に“十分な広さ”を選ぶほうが、動物にも家計にもやさしい選択です。
ケージ(おうちの広さと安全性)
サイズ(最重要)
- 1頭の場合:内寸100×60cm(0.6㎡)以上を推奨します。できれば120×60cm(0.72㎡)あると、本来の活発な行動が見られ、心身ともに健康的に過ごせます。
- 2頭の場合:最低120×60cmから。相性や性格を見ながら、さらに広くしてあげられると理想的です。
- 数で割るより、「頭数×0.35~0.40㎡+みんなの共有スペース」を目安にしてあげてください。
- “広さ=健康の源”です。モルモットは本来、長い時間を採食と探索に費やす動物。嬉しいときには体をひねって跳ねる「ポップコーンジャンプ」という行動を見せますが、これには十分なスペースが必要です。広い空間は、運動量を確保して肥満を防ぎ、足裏への負担を分散させます。また、退屈によるケージかじりなどの常同行動を減らすことにも繋がります。
- “広さ=におい対策”でもあります。広いほど汚れが一点に集中しにくく、足裏も乾きやすい=衛生的。大きめ一択が最終的に家計と時間の節約になります。
高さ・天井
- 高さは40~45cm以上、そして天井にはメッシュのパネルを必ずつけてあげましょう。
これはモルモット自身の脱走や落下事故を防ぐだけでなく、外部からの危険を守るためでもあります。例えば、家の中に他のペット(犬、猫など)がいる場合や、小さなお子さんがいるご家庭、また、上から物が落ちてくる不慮の事故からもモルモットを守る大切な役割を果たします。
素材
- 丈夫でお掃除しやすい金属ワイヤーと、おしっこが外に漏れにくい深めのトレーがセットになったケージが基本です。
- 「C&Cケージ」と呼ばれる、ワイヤーネットとプラスチック段ボール(プラダン、コロプラスト等)を組み合わせて作る自作ケージも非常に優れています。成長や頭数に合わせて自由に拡張でき、広さを確保しやすいのが最大の魅力です。
- 衣装ケースを改造して使用する方法もありますが、専門的な知識が必要です。通気性が著しく悪く、湿気やアンモニアがこもりやすいため、呼吸器疾患のリスクが高まります。また、夏場は熱がこもって熱中症の原因になり、透明度が低いと外からモルモットの様子の変化に気づきにくくなるという大きなデメリットがあります。初心者の方は避けたほうが賢明です。
- 床が金網になっているタイプのケージは原則使用しません。犬や猫と違い、モルモットの足裏には柔らかい肉球がなく、非常にデリケートな構造をしています。硬い金網の上で生活すると、属の凹凸で足裏に過度な圧力がかかり続け、趾瘤症(しりゅうしょう)という、治りにくい皮膚の潰瘍や感染症を引き起こす原因になります。使う場合は上に厚手マットやフリースを重ねて金網に直接触れないように完全被覆にしてください。
カギ
- 扉は、床に近くて横に開くタイプが出入りしやすく、モルモットにとって使いやすいです。
- モルモットは賢く、鼻先で器用にラッチを上げてしまうことがあります。ナスカンや小さなカラビナで二重にロックをかけ、脱走事故を防ぎましょう。
- ワイヤーの間隔は3cm以下のものを選びましょう。特に体の小さな若い個体は、わずかな隙間から脱走したり、頭や足が挟まって大怪我につながる危険があります。
レイアウトと出入口(暮らしやすい動線づくり)
同じケージでも、出入口のちょっとした段差やスロープの角度、天井の使い勝手で、暮らしやすさはぐっと変わります。モルモットはウサギのように跳躍が得意ではなく、その骨格は平地での生活に適応しています。“行きたい所へスムーズに行ける”ように工夫してあげるだけで、関節への負担やケガの心配が減り、毎日のお掃除もとても楽になります。
- 段差は2~3cm程度に抑えましょう。ウサギ用のケージには高いロフトが付いていることが多いですが、モルモットにとっては転落のリスクが非常に高い構造です。もし使用する場合は、緩やかなスロープを設置するなど、徹底したバリアフリー化が必要です。
- スロープは傾斜20度前後のゆるやかな角度に。モルモットは爪でひっかけて登ることが苦手なため、表面がツルツルしていると登れません。滑り止め(コルクマット、目の粗い布、ペット用の滑り止めシートなど)を必ず貼り付けてあげてください。
- 天井パネルが大きく開く、または取り外せるタイプだと、上からそっとモルモットを抱き上げたり、お掃除や物の配置換えをしたりするのが非常に楽になります。
- トレーの深さが12~15cmくらいあると、床材の飛び散りが格段に減り、お部屋を清潔に保てます。また、モルモットが床材に潜って遊ぶための十分な深さも確保できます。潜り癖が強い子では誤食しない素材選びをしてください。
【応用編】多頭飼い用のケージ
複数のモルモットを飼う場合、相性によってはケージを分ける必要があります。その際は、市販の仕切り付きケージ(例:三晃商会 イージーホーム80-PRO)を利用したり、100円ショップなどで売っているジョイント式のワイヤーネットを組み合わせて、スペースや頭数に合わせたオリジナルの仕切りを作るのも良いアイデアです。
床材の選び方(足と皮膚、呼吸器を守るために)
床材は、単に排泄物を吸収するだけでなく、「デリケートな足裏の保護」「皮膚を清潔に保つ」「呼吸器への刺激を減らす」「巣作りなど、本来の行動を促す」という、多くの大切な役割を担っています。素材ごとに長所と短所がありますので、おうちの環境やアレルギーの有無、お掃除のペースに合わせて、その子にぴったりの組み合わせを見つけてあげましょう。
- 代表例と使い分け
- 紙製床材
- 吸水性・消臭性に優れ、脚に優しいのが最大の魅力です。ただし、製品によっては製造過程で生じる紙の粉塵が多いものがあり、これがモルモットや人間の呼吸器を刺激し、アレルギーの原因になることがあります。開封時に軽く振るって、粉が舞いすぎないか確認し、低アレルギー・低粉塵と表記された製品を選ぶと安心です。
- アスペン(広葉樹のチップ)
- マツやスギなどの針葉樹に含まれる「フェノール類」という芳香成分は、モルモットの肝臓に負担をかける可能性が指摘されています。アスペンは広葉樹なのでその心配がなく、安全性の高い木製チップです。
- 牧草敷き
- 自然な環境に近くなりますが、おしっこで湿った牧草はカビや細菌の温床となり、アンモニアガスも発生しやすくなります。湿った牧草を食べてしまうと、消化器系の不調を引き起こす危険もあります。床材としてではなく、「食べるための牧草」として、専用のフィーダーや清潔な場所にたっぷりと用意してあげるのが、衛生的で健康的な方法です。
- フリース運用(フリースライナー)
- これは、布を洗濯しながら繰り返し使う、経済的でエコな方法です。しかし、正しく運用するには少しコツが要ります。構造は、一番下に防水シート、その上に吸水層(厚手のタオル、おねしょパッド、介護用吸水マットなど)、そして一番上に表面をサラサラに保つフリースを敷きます。
- 動物園でも実践される洗濯のコツ:洗濯機に入れる前に、屋外でフリースをよく振り、牧草のクズや毛をできるだけ払い落とします。その後、ペット用の洗濯ネットに入れ、洗剤は無香料で低刺激なものを使用します。フリース本来の撥水性を損ない、吸水性を低下させてしまうため、柔軟剤の使用は絶対に避けてください。
- かじり癖のある子には、布の繊維が腸に詰まる「腸閉塞」のリスクがあるため不向きです。
- ウッドペレット(トイレ用など)
- 吸水力が非常に高く、ケージの底、特におしっこをしやすい隅に敷くとアンモニア臭を強力に抑えてくれます。ただし、ペレットは硬く、水分を吸うと崩れて粉状になります。直接この上を歩かせると足裏を痛めたり、粉塵を吸い込む原因になるため、必ずペレットの上に紙製の床材やフリースなどを厚めに重ねて使用してください。
- 紙製床材
- 使わないでほしいもの・注意点
- ペットシーツの単独使用は厳禁です。
ペットシーツ内部の「高分子吸収ポリマー」をモルモットが誤って食べてしまうと、体内の水分を吸ってゲル状に膨張し、命に関わる深刻な腸閉塞を引き起こします。もし使うのであれば、すのこの下に敷くなど、モルモットの口が絶対に届かないように物理的に完璧にガードできる場合のみに限定してください。安全を最優先するなら、使用しないのが最も賢明な判断です。
- ペットシーツの単独使用は厳禁です。
- 床は“乾いていること”が最重要。乾けばにおい・足裏・皮膚・呼吸器の問題は大幅に減ります。湿りを作らない設計(吸水層+集約)を最優先に。
針葉樹と代替・交換頻度の目安
木製チップは“未処理の針葉樹(例:レッドシダー等)を避け”、できるだけアスペン(広葉樹)や“キルンドライ(高温乾燥)処理済み”の製品を選びましょう。
交換頻度の目安は、毎日スポット清掃+週1の全面交換(フリースは2〜3日に1回洗濯)。湿りや臭いを感じる前に先手で替えるのがコツです。
隠れ家(ハウス)の選び方と数
被捕食動物であるモルモットにとって、体を隠せる「自分の部屋」は、心からリラックスするために不可欠な、命綱とも言える場所です。「頭数+1個」を合言葉に、いくつか用意してあげましょう。素材や形によって居心地が変わるので、季節やその子の性格に合わせて、お気に入りの場所を選んであげましょう。
- 原則:頭数+1個以上。
これは、群れの中で社会的順位が低い個体が、優位な個体に追われた際にいつでも逃げ込める「予備の部屋」を確保するためです。隠れ家の数が足りないと、弱い個体は常に緊張を強いられ、慢性的なストレスの原因となります。複数の隠れ家は、ケンカを防ぎ、群れ全体の平和を保つための重要な工夫です。 - 素材:わら、チモシー、い草、無塗装の木材、コルクなど、すべてかじって食べても安全な自然素材のものを選びましょう。プラスチック製のハウスは、かじった破片を誤飲するリスクがあるほか、通気性が悪く内部が蒸れやすいという欠点があります。釘や強力な接着剤、有害な塗料が使われていないか、必ず確認してください。
- 消耗品と割り切る:ハウスをかじるのは、歯の伸びすぎを防ぐための正常で健康的な行動です。壊れてきたら、それは役目を果たした証拠。小さな破片を飲み込んでしまう前に、安全のために新しいものと交換してあげましょう。られる場所があると臆病な性格の味方となりストレスが減ります。
- トンネル型: モルモットは、もともと野生では地面に穴を掘って暮らしていた動物です。そのため、周りが囲われた狭くて少し暗い場所に入ると、とても安心します。面白いことに、中に入ったまま頭でハウスを動かし、まるでヤドカリのように移動する子もいます。
- 壺型: ペットショップのうさぎ用品コーナーでよく見かける、稲わらなどを編んで作られた壺型のハウスです。壺型の形状は周りを囲まれた狭い場所が大好きなモルモットにとって、最高の隠れ家になります。わらの自然な香りも彼らをリラックスさせてくれます。しかし、このハウスの本当の面白さはここからです。モルモットは、ただ隠れるだけではなく、このハウス自体を「かじって壊す」ことを楽しみます。
数と配置のコツ
数だけでなく“配置”も大切です。出入口が向かい合わず(にらみ合い防止)、逃げ込み先が複数方向にあるように置くと、優位な個体に追われても行き止まりになりにくいため、全体のストレスが下がります。
【重要】これは「消耗品」です!
このわら製ハウスを使う上で、一番大切な心構えです。
このハウスは、だんだんとかじられて形が崩れ、小さくなっていきます。それは決して悪いことではありません。むしろ、ボロボロになればなるほど、モルモットがそれだけたくさん遊んで、楽しんでくれた証拠です。
形が変わっていくのを楽しもう:最初はきれいな壺型だったハウスが、だんだん入り口が広くなったり、屋根がなくなったり…その変化の過程も、愛するモルモットが元気に暮らしている証として見守ってあげてください。
余談ですが、この形状はモルモットが非常に落ち着く反面、抱っこしようとすると嫌がって踏ん張り、なかなか出てきてくれないという飼い主泣かせな一面もあります。
- 木や牧草でできたハウス: 隠れ家としてだけでなく、齧って遊ぶおもちゃにもなります。筆者宅では木の枝でできたトンネルを与えたところ、夢中で齧ってしまい、数日で形が変わってしまうほどでした。 このように齧られることを前提に、安全な素材でできた消耗品と割り切って用意してあげると良いでしょう。
食器類(毎日のごはんを安全に楽しむ工夫)
お水とごはんは毎日の元気の源。食器類を快適に整えてあげると、においや汚れが減り健康チェックもしやすくなります。高さ・重さ・固定方法の3つのポイントを押さえ、事故の心配がないフィーダーを選んで安心して使える素敵な食卓をつくってあげましょう。
- 給水
- 給水ボトルが最も衛生的で基本となります。飲み口の先端が、モルモットが自然に顔を上げたときのお鼻から胸くらいの高さになるように調整しましょう。
- ボトル内のぬめり(バイオフィルム)は細菌の温床です。見た目はきれいに見えても、放置すると細菌が繁殖し、下痢などの原因になります。毎日、新鮮な水に交換し、ボトル内をすすぐのはもちろん、週に1回は専用のブラシと洗剤で飲み口のボール部分まで分解して徹底的に洗浄してください。動物園では、定期的に次亜塩素酸ナトリウムの希釈液などで消毒し、その後、成分が残らないよう流水で十分にすすぎます。
- 万が一の故障や、多頭飼育で水の取り合いが起こるのを防ぐため、ケージ内に2つ以上のボトルを設置することを強く推奨します。
- ボトルの“吸いにくさ”が癖で飲水減少を招くことがあります。2本設置でノズル径や高さを微調整すると、飲水量の個体差に対応できます。
- 給水は基本ボトルですが、浅くて重いボウルを台座で固定して併用すると、自然な飲み方ができる個体もいます(汚染・転倒対策が整う場合のみ)。
- 餌入れ(ペレット用)
- ある程度の重さがあり、簡単にはひっくり返せない陶器製か、傷がつきにくく衛生的なステンレス製がおすすめです。プラスチック製は軽く、すぐに動かされたり、かじられて傷ついた部分に細菌が繁殖しやすいため、あまり推奨できません。
- 牧草フィーダー
- 挟まり事故に最大の注意を払ってください。ワイヤーの間隔が狭まってV字型になるタイプのフィーダーや、金属製のボールに牧草を詰めるタイプは、モルモットが頭を突っ込んだ際に抜けなくなり、窒息死するという悲しい事故が実際に起きています。スリット幅が広く、体のどの部分も挟まる危険のない、安全な設計のものを選びましょう。
- 挟まり防止の目安として、フィーダのスリット幅は約3〜4cmを基準にすると安全寄りです。
- 近年では、床に置くタイプの牧草入れ(牧草パーク、牧草キッチンなど)が主流です。これは、モルモットが最も自然な姿勢(首を少し下げた状態)で牧草を食べることができ、歯の正常な摩耗を促す効果も期待できます。浅いトレーなどに牧草をふんわりと入れてあげるだけでも十分です。
【体験談】牧草フィーダー導入のメリット: 床に直接牧草を敷くスタイルから牧草フィーダーに変えたところ、以下のような多くのメリットがありました。
- 排泄物と牧草が混ざらないため、ケージ内の臭いが大幅に軽減された。
- 汚れた牧草を毎日拾う掃除の手間が減少した。
- お尻が汚れにくくなり、衛生的になった。
- 無駄になる牧草が減り、経済的になった。
キャリー・防災セット・応急処置キット(もしもの時の備え)
病院への通院や引っ越し、そして万一の災害時にも、「いざという時に、すぐに動ける準備」があると、飼い主さんもモルモットも安心です。丈夫なハードキャリーと、最低3日分の備え、そして簡単な応急セットをひとまとめにしておきましょう。普段からキャリーに慣れておくことが、いざという時のストレスを大きく減らす鍵になります。
- キャリー:衝撃に強く、掃除がしやすいプラスチック製のハードタイプが最適です。上部が大きく開くものは、モルモットの出し入れがスムーズにできます。
- 慣らし方:普段からケージの近くや部屋んぽスペースに扉を開けた状態で置いておき、自由に出入りできるようにしておきましょう。中に好きなおやつや牧草を入れておくと、「キャリー=安全で良いことがある場所」と学習してくれます。
- 保温・冷却は“片側だけ”。自分で暑い・寒い側を選べる余地が安全です。
- 防災セット:災害発生後、支援物資が届くまでに最低3~5日はかかると想定し、その間の食料と衛生用品を準備します。牧草、ペレット、療法食、常備薬に加え、給水ボトルから飲むのが苦手な子のために、シリンジや浅いお皿も入れておくと安心です。
- 応急処置キット:爪切り、止血剤、動物病院で処方された消毒液などに加え、強制給餌用のシリンジと、獣医師に指示された際に使用する流動食の粉末(クリティカルケアなど)を常備しておくと、食欲が落ちた際の初期対応に役立ちます。ただし、これらは必ず獣医師の診断と指示のもとで使用してください。
体重計とヘルスチェック(言葉のない彼らのサインを見つける)
モルモットの健康管理において、体重測定は「命綱」とも言えるほど重要です。彼らは不調を隠す天才。しかし、体重計の数字は嘘をつきません。週に一度の体重測定を習慣にすることで、見た目ではわからない病気の兆候を誰よりも早く察知し、手遅れになる前に行動を起こすことができます。ここでは、正しい体重の測り方と、併せて行いたい日々のチェックポイントを詳しく解説します。
- 準備するもの:体重計
- 種類:必ず1g単位で測定できるデジタルスケールを用意してください。一般的に「キッチンスケール」として販売されているものが最適です。人間用の体重計では、わずかな変化を捉えることはできません。
- 測るための容器:モルモットがじっとしていられるように、プラスチックのボウルや小さな箱、キャリーケースの底部分などを用意します。
- 正しい体重の測り方(動物園でも実践する正確な方法)
- まず、体重計の上に空の容器だけを乗せ、表示をゼロにする「風袋引き(TARE)機能」を使います。これにより、容器の重さを引く手間がなくなります。
- モルモットを優しく容器の中に入れます。落ち着かない場合は、少量の好物(小さな野菜のかけらなど)で気を引くとスムーズです。
- 数字が安定したところで、1g単位まで正確に読み取り、必ず記録します。
- 毎週、同じ曜日、同じ時間帯(例:日曜の朝、ごはんの前など)に測定することで、食事や排泄による誤差が少なくなり、より正確な変化を追うことができます。
- 記録の重要性と「危険なサイン」
測定した体重は、必ず手帳やスマートフォンのアプリなどに記録し、グラフ化すると変化が一目でわかります。- 注意すべきサイン:
- 継続的な減少:2~3週間にわたって、毎週少しずつでも体重が減り続けている。
- 急激な減少:1週間で50g以上の体重減少が見られた場合。これは非常に危険なサインです。成体(体重約1kg)にとっての50gは、体重60kgの人間でいう3kgに相当します。見過ごすことはできません。
- 注意すべきサイン:
これらのサインが見られた場合は、「もう少し様子を見よう」とは思わず、直ちにエキゾチックアニマルを診療できる動物病院に連絡し、受診してください。 その際、記録しておいた体重のデータが、獣医師にとって非常に有力な診断材料となります。
- 体重測定と合わせて行いたい、毎日のヘルスチェック
体重測定は週に一度の習慣ですが、以下の点は毎日、ケージのお掃除やごはんをあげる際に、さりげなくチェックしてあげましょう。- 目:目ヤニや涙で濡れていないか。白く濁っていないか。
- 鼻:鼻水で汚れていたり、濡れていたりしないか。「プスプス」というくしゃみが多くないか。
- 歯:口元から歯が伸びすぎていないか。よだれで口の周りや前足が濡れていないか(不正咬合の疑い)。
- お尻周り:糞や尿で汚れていないか。下痢をしていないか。
- 全身の触診:抱っこした時に、しこりや腫れ物がないか、体を優しく撫でて確認する。痛がるそぶりを見せないか。
- 食欲と行動:ペレットや野菜をすぐに食べたか。牧草を食べる量が減っていないか。元気に動き回っているか、ケージの隅でじっとうずくまっていないか。
- 糞と尿:糞の大きさはいつも通りか(小さく、量が少ないのは消化器不調のサイン)。尿の色は正常か(血が混じっていないか)。
これらの日々の観察と、週に一度の正確な体重測定を組み合わせることで、私たちは言葉を持たない彼らの「助けて」のサインを、早期に、そして確実に見つけてあげることができるのです。
補足アドバイス(ご家族の皆様へ)
ここからは、モルモットとの暮らしがもっと楽しく、スムーズになる「ちょっとしたコツ」です。難しいことは何もありません。「広く、乾いていて、隠れ家がたくさんある」この3つを基本に、彼らの習性を理解することで、トラブルはぐっと減ります。
- 広さは愛情」を忘れずに
広いケージでのびのびと過ごすモルモットは、嬉しい時に「ポップコーンジャンプ」を見せてくれます。これは心身ともに健康で、安心している証拠です。その姿を見られることこそ、飼い主さんにとっての最高の喜びの一つです。 - 「サラサラで清潔」が健康を守る近道
湿った不衛生な床は、趾瘤症(ポドダーマティティス)の最大の原因です。足裏の皮膚のバリア機能が弱まり、そこに常在菌が感染して炎症を起こします。一度発症すると完治が難しく、痛みを伴う病気です。毎日のこまめな掃除が、何よりの予防薬です。 - 「足裏チェック」は、小さなサインを見逃さないための大切な時間
動物園では、動物たちが自ら協力して健康管理を受けられるようにする「ハズバンダリートレーニング」を行います。ご家庭でも、抱っこに慣れさせ、優しく声をかけながら足の裏を見せてくれたらおやつをあげる、という練習を続けることで、モルモットも飼い主さんもストレスなく健康チェックができるようになります。 - 「病院へ行く勇気」と「事前の準備」を
モルモットは、敵に弱っていることを見せないように不調を隠す本能があります。飼い主さんが「何かおかしい」と感じたときには、すでに病気が進行していることも少なくありません。「週に50g以上の体重減少」「食欲不振」「うんちが小さい、または出ていない」「呼吸が速い、苦しそう」などは、緊急事態のサインです。夜間や休日に対応してくれる、エキゾチックアニマルの診療が可能な動物病院を、平穏なうちから必ず探し、リストアップしておきましょう。それが、いざという時にあなたのモルモットの命を救うことになります。 - 「隠れ家は複数」が合言葉
これは、ケンカの予防だけでなく、それぞれのモルモットが「自分だけの時間」を過ごすための大切な配慮です。私たち人間と同じように、いくら仲が良くても四六時中一緒では疲れてしまいます。一頭で静かに休みたい時、そっとしておいてほしい時に避難できる場所があることで、モルモットは心の平穏を保つことができます。 - 「におい対策」は「お掃除しやすい工夫」から
ケージのにおいの主な原因は、尿が分解されて発生するアンモニアです。このアンモニアガスは、ただ臭いだけでなく、モルモットの繊細な呼吸器の粘膜を刺激し、くしゃみや鼻水、重篤な呼吸器疾患の原因となります。においを根本から断つには、消臭スプレーに頼るのではなく、「汚れを1か所に集めて、そこを集中して掃除する」という設計が最も効果的です。「牧草キッチン」のように、食事と排泄の場所をある程度まとめることで、掃除の手間が格段に減り、ケージ全体を常に衛生的に保てます。 - 「夏は無理をさせない」エアコンは命綱です
モルモットの祖先は、涼しい高地に生息していたため、暑さには非常に弱いです。体温調節が得意ではなく、汗をかくこともできません。室温が28℃を超えると熱中症のリスクが急激に高まります。夏場は24時間エアコンを稼働させ、室温を18~24℃、湿度を40~70%に保つことが、彼らの命を守るための目安です。ひんやりプレートや凍らせたペットボトルは、あくまで補助的なもので、部屋全体の温度を下げる力はありません。ぐったりしている、呼吸が速く荒い、よだれを垂らすなどの症状は熱中症のサインです。すぐに涼しい場所へ移し、体を冷やしながら動物病院へ連絡してください。 - 「かじる」のは正常な行動。安全なかじり木を
モルモットの歯は一生伸び続けます。硬い牧草や安全なかじり木をかじることで、歯が適切な長さに削られ、「不正咬合(ふせいこうごう)」という病気を予防しています。不正咬合になると、歯が伸びすぎて口の中に刺さったり、うまく食べられなくなったりして、命に関わることもあります。かじり木は、彼らにとって健康維持に不可欠な「デンタルケア用品」なのです。ただし、電源コードや観葉植物、塗料が塗られた家具など、かじってはいけない危険なものが周りにないか、部屋んぽの前には必ず確認する習慣をつけましょう。 - 家族で役割分担を。そして情報を共有しましょう
毎日のごはんやお掃除、週に一度の体重測定など、ご家族で役割分担をすると、無理なく楽しく続けられます。そして、もう一つ大切なのが「情報の共有」です。「今日、〇〇ちゃんのうんちが少し小さかったよ」「最近、水を飲む量が増えた気がする」といった、日々の小さな気づきを家族で共有するノートを作っておくのがおすすめです。獣医師にとっても、そうした日々の記録は、病気の原因を探るための非常に貴重な手がかりとなります。
よくあるQ&A
- Q1:ペットシーツをかじってしまいます。どうすればいいですか?
- A:直ちに使用を中止し、モルモットの口が届かない方法に見直してください。 ペットシーツ内部の「高分子吸収ポリマー」は、水分を吸収してゲル状に膨らむ化学物質です。これを誤食すると、体内で膨張し、命に関わる深刻な腸閉塞を引き起こす危険があります。安全な対策は、すのこの下に敷くなど物理的に完全にガードするか、そもそも使わずに紙製の床材とウッドペレットを組み合わせる方法に切り替えることです。安全が何よりも優先です。
- Q2:ケージの金網をずっとかじっています。やめさせる方法は?
- A:金網をかじる行動には、いくつかの理由が考えられます。
- 退屈のサイン:ケージが狭い、遊ぶものがないなど、刺激が足りないのかもしれません。部屋んぽの時間を増やしたり、隠れ家やトンネルの配置を変えたり、新しいかじり木を与えたりして、環境に変化をつけてみましょう。
- 要求のサイン:「ごはんが欲しい」「外に出たい」といった飼い主さんへのアピールです。かじるたびに応えてしまうと学習してしまうため、まずは牧草が常に十分にあるか確認し、要求に応えるのではなく、時間を決めて接するようにしましょう。
- 牧草不足のサイン:モルモットは常に何かを食べて口を動かしている動物です。牧草が足りないと、手持ち無沙汰で金網をかじることがあります。牧草は24時間いつでも食べられるように、常にたっぷりと補充してください。
- A:金網をかじる行動には、いくつかの理由が考えられます。
- Q3:床材を替えたいのですが、急に変えても大丈夫ですか?
- A:急に変えるのは避け、1週間ほどかけてゆっくり移行させてあげてください。 モルモットは非常に繊細で、環境の変化にストレスを感じやすい動物です。床材が変わると、足の感触やにおいが大きく変わるため、不安になってしまうことがあります。最初は、古い床材を3分の2、新しい床材を3分の1ほど混ぜて敷き、数日ごとに新しい床材の割合を増やしていく、というように段階的に慣らしてあげましょう。
- Q4:トイレは覚えますか?
- A:犬や猫のように、特定の場所で完璧にトイレをすることは、残念ながらほとんどありません。 モルモットは、リラックスしている場所や食事をしている場所で排泄する習性があります。ただし、ケージの隅など、特定の場所を好んでトイレにする傾向はあります。その「お気に入りの隅」にウッドペレットを敷いて吸収力を高めたり、そこだけ重点的に掃除したりすることで、ケージ全体の衛生管理はぐっと楽になります。「だいたいこの辺でする」くらいの大らかな気持ちで見守ってあげてください。